補食🍙
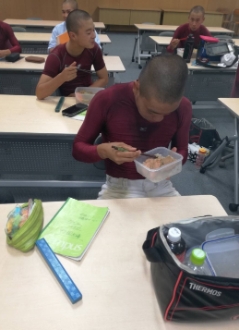
3度の食事で足りないものを補う『補食』です‼
補食は手軽に食べられるおにぎりやサンドイッチ、バナナやチーズなどが主流ですが、このチームの選手たちは補食用のお弁当を持ってきて、合間を見てはこまめに食べています🍱
食べる力をつけるためにも補食は必須🍙🍙🍙
ちなみに選手それぞれに適した食事量はアドバイス済みです😉
食べる力をつければ身体が変わり、身体が変われば心も変わります❕
選手諸君、毎日2つのお弁当を作ってくださる親御さんに感謝して、これからも頑張っていきましょう👦
ジュニアアスリート専門!正しい知識と習慣で勝てる身体が手に入る
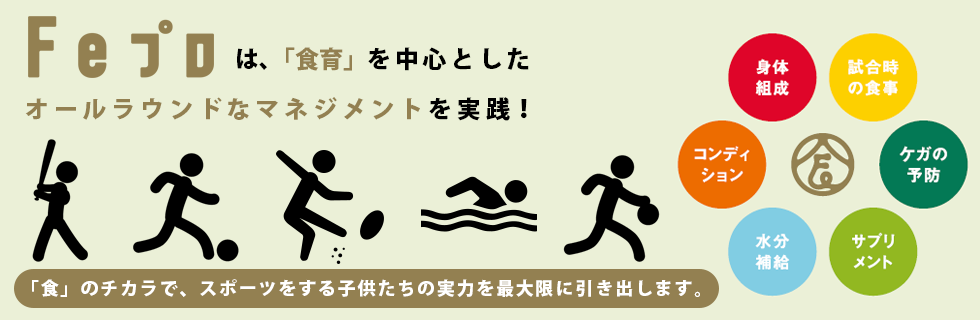
ホーム ≫ ブログページ ≫
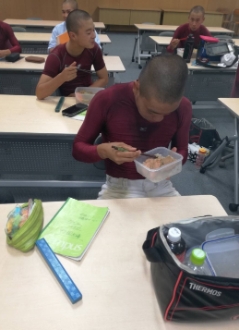

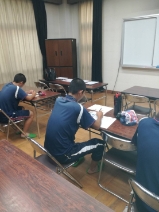
夏で3年生が引退し、責任感が出てきた選手たち!
3年生が抜けると、1、2年生が急激に成長していきます😊
勝つために、今回も「食育」と「アスリートヨガ」で積極的に身体づくりを取り組んでいます。
特に県内屈指の二遊間❕
全国屈指になるために妥協がありません。
「今年中にBMIを23.5にします」、「今月、除脂肪体重を1.5㎏増量させます」など、それぞれが口に出して目標を掲げていました💪
目標を公言することは良いことですよね。
食べる量とタイミングをしっかり考えて日々を過ごしていきましょう‼
この背中、来年には更に逞しく、大きくなっていることでしょう😉
はじめに
スポーツ栄養コラムの第4回目にして、ようやくたどり着きました「アスリートにとっての食事の意義・目的」というテーマです。
今回は、選手目線で食事の考え方について解説したいと思います。
目次
・アスリートにとっての食事の意義・目的とは
・おわりに
◆アスリートにとっての食事の意義・目的とは
これまで競技レベルも様々、年齢も様々、多くの選手サポートをしてきましたが、アスリートの食事の目的は最終的には3つに絞ることができます。
①身体づくりのため
毎日の練習や試合で十分な「回復」を促し、日々リカバリーをして身体づくり(筋肉量・筋力を増やす、体力をつける)をすることです。日々、適切な回復をすることで毎日の練習の質を高め、結果的には競技力向上にも繋がります。
また、成長期の選手は適切な成長を促すためにも十分な栄養補給が必要です。
②競技能力を発揮するため
毎日の練習の成果を「試合」や「競技会」で発揮するための栄養補給です。今までの積み重ねてきたことを本番でもできるように、日々の疲労をリセットする、「試合」に向けた準備をすることです。
大切なことは、日々の身体づくりができていることが「大前提」になります。普段できないことが突然できるようになる「魔法の食べ物」は存在しません。
③体調管理(コンディショニング)のため
日々の身体作りができていれば、自然とできてくることですが、例えば夏の熱中症予防、冬の風邪予防、貧血予防など、アスリートは一般の方よりも栄養不足に陥りやすい状態になります。また、なるべく起こってほしくはないですが怪我や障害もゼロとは言い切ることはできません。
そういったことを最小限に食い止める、回復を最大限に高めるためにも栄養・食事が関係しています。
◆おわりに
今回はアスリートにとっての食事や栄養の目的・意義についてお話し致しました。最後に3つの目的をよく読み直してもらえればと思いますが、最も大切なことは「日々の身体づくり」のためです。
適切な身体づくりができていれば競技力向上にも繋がりますし、怪我のしにくい身体ができます。食事は薬ではありませんので、いきなり成果が出るということも期待できません。
だからこそ、毎日の小さな積み重ねが大切です。目に見えない、記録に現れないからといって投げ出すのではなく、自分の力として積み重ねていけるといいですね。


はじめに
このコラムを書き始めて3回目になりました。
皆さんのスポーツ活動は「競技」でしょうか?それとも「レクリエーション」でしょうか?何の為にスポーツをやり、そして、何を目指してスポーツを続けているのでしょうか?
今回は体育(スポーツ)を紹介し、食の考え方についてより深く考えるきっかけになればと思います。目次
・スポーツをするということ
・おわりに
◆スポーツをするということ
今から100年以上前に日本体育協会を設立に導いた嘉納治五郎先生は次のように述べられました。「国の盛衰は、国民の精神が充実しているか否かによる。国民の精神の充実度は国民の体力に大きく関与する。そして、国民の体力は国民一人ひとり及び関係する機関・団体等が体育(スポーツ)に関して、その重要性をどのように認識しているかによる。
我が国の体育(スポーツ)の振興体制は、欧米諸国に比べ著しく劣っており、必然的に青少年の体格も劣弱の状況である。そのため、一大機関を組織し、体系的に国民の体育(スポーツ)の振興を図ることが急務である。以下、略(引用:日本体育協会ホームページ、創立100周年記念事業より「日本体育協会の創立趣意書」参照)。
体育・スポーツは国民一人一人の体力、精神を活き活きとさせて、国を元気にしよう!という考え方が100年以上前には存在していたのです。最近ではスポーツを「やる人」と「全くやらない人」という二極化が見られますが、「体」を「育てる」と書く「体育」を見直してもらえればと思います。
しかし、皆さんはスポーツの本質は知っておく必要があります。スポーツは体を「破壊」し、そして「(超)回復」させる、この過程があるからこそ、体力向上や競技力向上に繋がります。行き過ぎた「勝利至上主義」は「回復」を妨げてしまい、むしろ疲労がたまり、最悪のケースでは怪我や障害に繋がります。
ここで大切になるのがスポーツ栄養学です。「体育」と「食育」、この2つの視点から皆様の「回復」を最適にし、国民としての体力向上、競技者としての競技能力向上に寄与できるように今後も情報発信をしてまいります。
◆おわりに
少し方向性がそれてしまいましたが、色々な視点からスポーツ栄養学を見てもらえれば幸いです。
なかなか本題に入らないと思っている皆様、次回コラムでは「アスリートにとっての食事の目的」についてお話したいと考えております。
次回もお楽しみに!!

はじめに
スポーツ栄養コラムの第2回の記事です。
スポーツの秋になり、各地では運動会、そして部活動では卒業生が引退して世代交代が進んでいる時期でしょうか。
筆者がスポーツの秋を感じるのは10月10日(体育の日)ですが、今は10日とは限りませんね・・・と言っていると年代がバレてしまいそうです(笑)
目次
・意外と知られていないスポーツ栄養の歴史
・おわりに
◆意外と知られていないスポーツ栄養の歴史
今回はスポーツ栄養の歴史と皆さんに豆知識を提供致します。さて日本で「スポーツ栄養」という言葉が現れたのは1990年(平成2)からだそうですが、皆さんはご存知だったでしょうか?
当時は競技力向上のために「栄養素」をどのように摂るかという考え方で食品やサプリメント市場の拡大が進みました。その後、様々な議論が繰り返され、日常の食事を差し置いてサプリメントや補助食品だけを利用することが問題視され、現在では日々の食生活(単に食事だけでなく、運動面、休養面を含む)全般を改善することが重要であるといわれています。
しかし、未だにこの初期のスポーツ栄養のイメージから脱却できていないスポーツ現場は多く見られます。まずは指導者や専門家、保護者が正しい知識を得て、子供達の食育に当たらなければいけないかもしれませんね。
さて、話はガラリと変わりますが、2020年の東京五輪ではなく、1964年の東京五輪でも食の「おもてなし」にこだわりがあったのはご存知でしょうか?
当時の選手村では世界90カ国、約7000名の方々に世界中の料理、のべ60万食を振舞うことが決まっていました(参照:日本経済新聞, 2013年10月7日付)。のちに帝国ホテルの総料理長となる村上氏が料理を作るために試行錯誤したそうです。その想いの中には、単に世界に日本の価値を示すだけではなく、日本を訪れた各国の選手が普段食べているものを食べて、競技に集中してもらえるようにという気持ちがあったそうです。
毎日食べるものだからこそストレスにしたくない・・・日本のスポーツ栄養はこの時からすでに始まっていたのかもしれません。
◆おわりに
スポーツ栄養はまだまだ発展途上の学問です。そして2000年代に入り、多くの情報が世に出るようになり、インターネット等を通じて誰でも簡単に知る機会が増えました。しかし、正しい情報は何か、相反することいわれると結局何が正しいのかって混乱してしまいますね。
最後に10月10日(旧 体育の日)は、1964年東京五輪の開会式の日だったんですね・・・こちらも皆さまご存知でしたか?それでは、今後もこのような形で少しずつ正しい情報を整理・解説して参りますので、お楽しみ頂ければと思います。

株式会社FeプロモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!